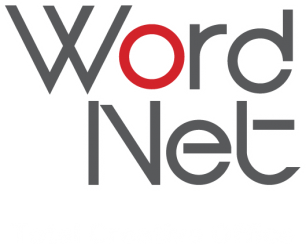ここ数年の事務所界隈
ずっと工事の音がしている。
安堂寺町に引っ越した頃
事務所ビルの通りには
古い町家がたくさんあった。
間口は狭いけれど
弊社のあるビルと同じ奥行き。
表通りは店舗があり
中庭を挟んで住居スペースと
昔ながらの「うなぎの寝床」
そんな町家がたくさんあった。
ここは熊野街道と
暗越奈良街道が重なる通り。
往時は八軒屋浜からの旅人が
賑やかに行き交う街道だった。
数年前、ビルの隣りにあった
古い電気屋さんの建物が無くなり
一時、駐車場になったが
昨年から工事が始まり
もうマンションが立った。
マンションの工事が始まった頃
埋蔵文化財が見つかり
しばらく調査をしていたけれど
掘って記録して元に戻し
その上にマンションが立った。
このあたり上町台地は
古代遺跡、難波宮跡、石山本願寺
豊臣の大坂城の上に徳川の大坂城。
都市や経済発展の歴史とともに
明治・大正・昭和にかけての
軍都大阪の遺構が残る場所でもある。
何層にも重なる歴史があり
どこを掘っても何かでてくる。
それを都度調査や保存は難しい。
よくわかっているけれど残念。
スマホに8年前の写真があった。
お隣りの電気屋さんの看板は
東面に「東芝カラーテレビ」
西面に「東芝電子レンジ」
通りの街灯が徐々にLEDにかわり
旧街道の往時を偲べる風景も
記憶と記録になっていく。
まだまだ残る風情を風景を
しっかりと記憶に刻んでおこう。