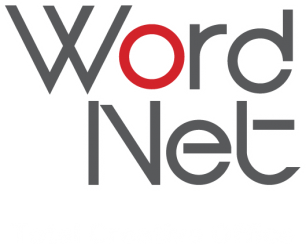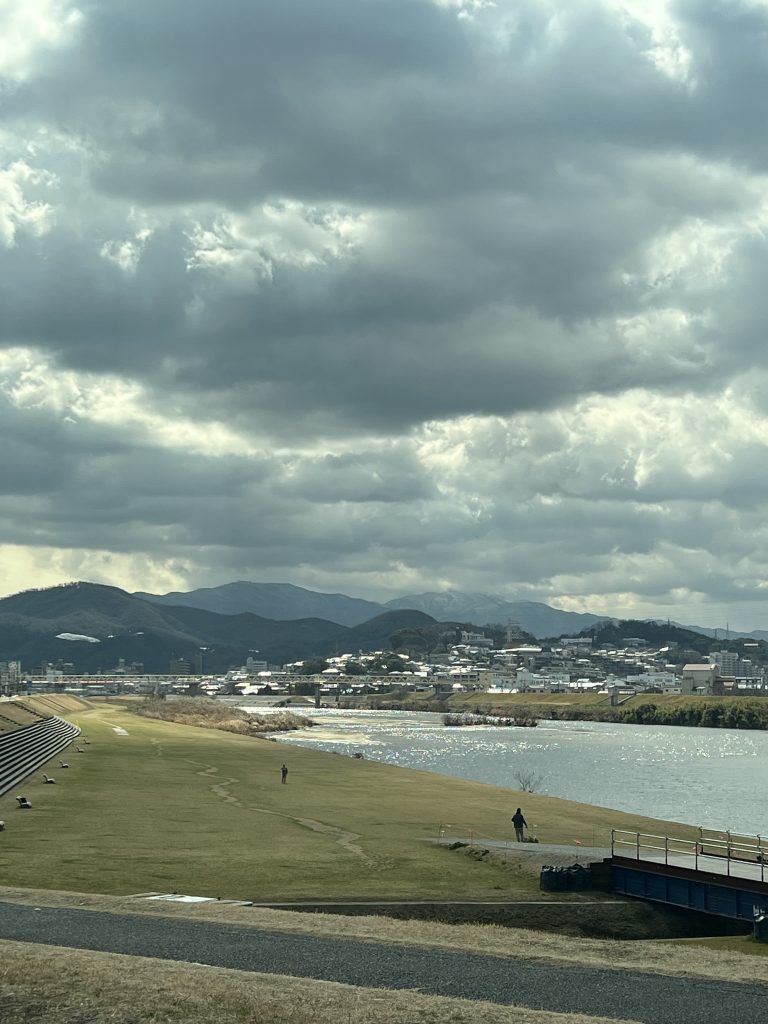昔「立売堀」でバイトをしていた。
まだPC98や富士通OASYSの時代。
この業界の入り口にいた。
その頃の話を…ではなくて
今日は難読地名の話。
この「立売堀」読めますか?
大阪には難読地名が多い。
なかには「それはないわ~」
と言いたくなるものもある。
でも難読地名は
歴史的事象、地形や自然、
外来語などに由来する
知ると納得するものが多いし
知ると読み方を忘れない。
たとえばこの
「立売堀=いたちぼり」
大坂冬の陣・夏の陣で
壕を掘った伊達家の陣地の跡を
掘り進めて出来た立売堀川の名残り。
でも字が違いますよね。
最初は「伊達堀=だてぼり」と
読んでいたものが「いたちぼり」
呼ばれるようになり
(間違って読む人が多くて
そうなっちゃった気も…)
その後、伊達堀の一帯で
材木が立売されるようになり
「立売堀」の文字に。
そして読み方はそのままに。
この立売堀川は埋め立てられて
いまはこの地名が残るだけ。
その他の大阪の難読地名
「放出=はなてん」
「枚方=ひらかた」
「土師=はじ」
「柴島=くにじま」
「中百舌鳥=なかもず」
「喜連瓜破=きれうりわり」
「杭全=くまた」
上に並べた地名だけでも
神話に基づく地名や
ドロドロした由来もある。
地名の由来を調べると
その土地の歴史が見えてきたり
新しい発見と出会えます。
お住まいやお勤め先の地名
ちょっと調べてみませんか。